患者様の気持ちや糖尿病に対する考え方をよく聞くことを心がけています。
患者様が自ら治療に取り組んでいけるようサポートします。
全体イメージ図


糖尿病の専門施設として、糖尿病患者さんそれぞれに最も適した治療法を提案し、患者さん本人が、治療に取り組んでいけるようにサポートします。そのために、糖尿病専門医だけではなく、日本糖尿病療養指導士(CDEJ)の資格を持つ専門スタッフ(看護師、薬剤師、管理栄養士、理学療法士)や糖尿病看護認定看護師、また臨床心理士といった多くの経験と実績を積んだコメディカルスタッフが、それぞれの専門性を生かし、チーム医療を行います。
また、糖尿病は高齢者の4~5人に一人罹患しているといわれており、昨今問題となっている高齢化においても糖尿病は避けては通れない病気です。当病院には地域包括ケア病棟があり、当センターでは、この病棟を利用して、高齢者糖尿病患者さんが在宅もしくは施設でも、なるべく負担なく糖尿病と付き合えるような方法を提案しています。
当科では、糖尿病診療ガイドライン2019と最新の知見を含め診療を行っています。
当センター外来では、専門ナースがまず療養面談を行い、患者様とともに考え、その後に医師の診察が行われるスタイルを取ります。
初診や紹介の患者様は、数ヶ月間当センター外来で指導を受けるか、あるいは短期入院により、食事指導や療養指導、薬物調整を受けて頂き、その後はかかりつけ医の先生と当センターで連携を取りながら診ていきます。患者様は6ヶ月毎にセンターを受診し、食事や療養指導を受け、かかりつけ医の先生と専門施設の協力のもとで良い治療を継続することが出来ます。かかりつけ医がない場合、連携施設を当センターから逆紹介するか、慈愛会の糖尿病専門クリニック(七波クリニック、慈愛会クリニック)での定期通院になります。
また、インスリンポンプ持続注入療法(CSII)や、連続した血糖測定が可能とする持続血糖モニタリング(CGM・FGM)を使用し、より専門的に厳格な血糖コントロールも行っております。
血糖コントロール不良な患者さんに対しては、まず強化インスリン療法を行い、膵臓を休ませます。その後患者さんそれぞれにあった薬剤の調整を行います。
また、当科では外来では十分に指導できないため、下記教育入院を行っております。それぞれ患者さんの状況にあわせて選択でき、患者さん自ら実生活の中で無理なく継続できる方法を学び取っていただけるような内容となっています。
また、高齢者糖尿病患者さんに関しては、在宅や施設での生活に極力支障がないような治療法を模索するだけではなく、患者さんやその家族の負担が軽減できるように環境調整を行います。
患者様の教育入院メニュー
病院に通うことは精神的にも、時間的、体力的にも大変だと思います。
私たちは、そのような苦痛がわずかでも軽減できるよう努めています。
ここ十数年の眼科治療の進歩によって、今まで治すことのできなかった多くの病気が治せるようになっています。他の身体の病気と同じように、早期に発見して適切な治療をすることがとても大切です。糖尿病網膜症や緑内障などは、現在でも失明原因の一番に挙げられる難しい病気ですが、適切な時期にしっかりとした治療を受ければ、失明を防げる病気です。
残念ながら多くの患者様は、病気を十分に理解できていなかったり、誤った判断をしたりして、必要な時期に適切な治療を受けられず手遅れになっていることが少なくありません。診療に際しては、間違った理解で見えなくなってしまうようなことがないように、病気についてわかりやすく丁寧に説明し、十分理解していただけることをなにより大切にしています。
糖尿病や腎臓病、血液の病気など目に合併症を起こす患者様が多くいます。このような場合は、特殊な機械を用いた治療となります。
全身合併症のある患者様の治療にいち早く取り組み、治療実績を積み重ねております。また、専門の診療科との連携で総合的な治療を行っています。
当科では、下記学会・研究会等の診療ガイドラインに沿った診療を行っております。
・黄斑部毛細血管拡張症2型診療ガイドライン 厚生労働科学研究費補助金難治性疾患政策研究事業「網膜脈絡膜・視神経萎縮症に関する調査研究」研究班
・緑内障診療ガイドライン 日本緑内障学会
・アレルギー性結膜疾患診療ガイドライン 日本眼科アレルギー学会
・糖尿病網膜症診療ガイドライン 日本糖尿病眼学会
・眼局所用抗菌薬の臨床評価方法に関するガイドライン 日本眼感染症学会
・ぶどう膜炎診療ガイドライン 日本眼炎症学会
・ドライアイ診療ガイドライン ドライアイ研究会
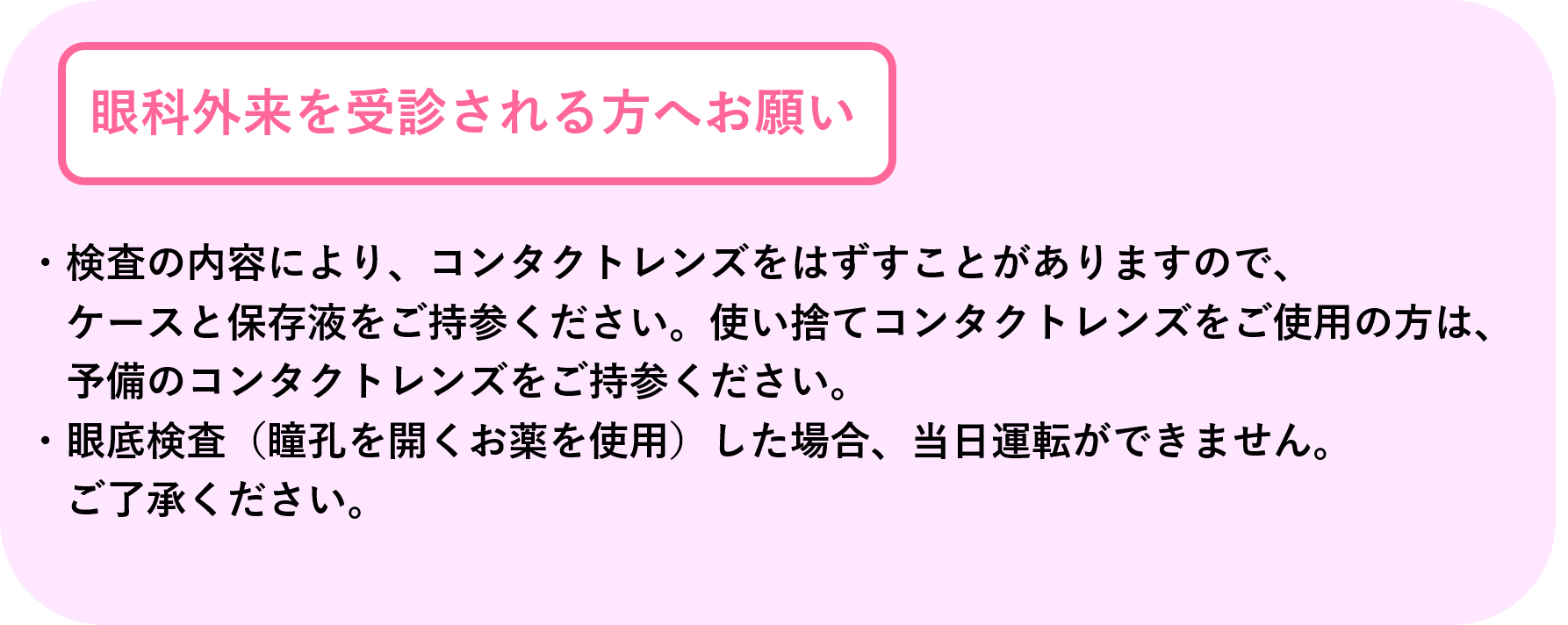
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 鎌田 上久保 |
鎌田 田川 |
鎌田 上久保 新中須 (第3週) |
新中須 田川 |
松下(敬) 大重 |
新中須 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 水島(崇) 水島(由) |
水島(崇) 藤原 水島(由) |
土居(隔週) 水島(崇) 藤原 |
水島(崇) 藤原 土居(第2週) |
鹿大医師 | 第1週 当番医師 第2週当番医師 第3週鹿大医師 第4週当番医師 第5週当番医師 |
| 午後 | 水島(崇) 水島(由) |
水島(崇) 水島(由) 藤原 |
土居(隔週) 水島(崇) 藤原 |
藤原 (第1週を除く) |
鹿大医師 | ― |
初期の糖尿病の教育から、眼や腎臓、足壊疽、動脈硬化など合併症を持った重症の糖尿病まで、どのような糖尿病にも対応できます。
糖尿病には食事療法、運動療法、薬物療法などの治療方法があります。
| 項目 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 入院患者数 | 534 | 548 | 520 | |
| 平均在院日数 | 16.90 | 15.38 | 18.4 | |
| 患者数 | 初診外来 | 849 | 854 | 721 |
| 入院 | 534 | 548 | 520 | |
| 紹介施設 | 303 | 479 | 408 | |
| 地域連携施設 | ||||
| 外来 | 145 | 160 | 151 | |
| 金土コース(1泊2日) | 28 | 17 | 9 | |
| 腎保護コース(2泊3日) | 36 | 36 | 27 | |
| 項目 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|---|
| 手術 | 緑内障関連手術 | 3 | 0 | 4 |
| 硝子体手術 | 110 | 79 | 86 | |
| 水晶体再建術 | 481 | 551 | 511 | |
| テノン氏嚢内注射 | 26 | 24 | 21 | |
| 硝子体内注射 | 502 | 472 | 515 | |
| 汎網膜光凝固術 | 168 | 161 | 131 | |
| 後発白内障切開 | 83 | 72 | 79 | |
| 翼状片手術 | 5 | 6 | 8 | |
| 外眼・角膜・涙道手術 | 23 | 6 | 20 | |
糖尿病は治療しないで放置していると、やがて失明や血液透析、脳梗塞、心筋梗塞、足の切断にいたります。しかし、しっかりと治療する術を身につけることで、これらの合併症は回避することが可能です。糖尿病の治療は日常生活の中で、しかも生涯継続していく必要があります。そのためには、糖尿病にしっかりと向き合って、無理せずに続けていける自分に合った方法を見つけていくことが重要です。私どもの仕事はそれをサポートしていくことだと考えています。
目は、外からの情報の80%を得るといわれている大切な場所です。当院は、糖尿病をはじめとして全身合併症からくる重症の眼疾患の患者様がとても多い病院です。このような病気で見えづらくなる人が一人でも少なくなればという思いで働いています。 不安に思うことやお聞きになりたいことがあれば、遠慮なくお話しください。

鎌田 哲郎
かまだ てつろう
名誉院長
慈愛会糖尿病センター長
専門
医学博士
日本内科学会認定医
日本糖尿病学会認定医
日本糖尿病学会研修指導医
鹿児島大学医学部臨床教授
鹿児島大学医学部非常勤講師

新中須 敦
しんなかす あつし
副院長
糖尿病内科主任部長
専門
医学博士
日本内科学会専門医
日本糖尿病学会専門医・指導医
内分泌学会専門医・指導医
プライマリーケア学会認定医・指導医
日本動脈硬化学会専門医

松下 敬亮
まつした けいすけ
専門
日本糖尿病学会専門医

仮屋 毅彦
かりや たけひこ
糖尿病内科医員

上久保 定一郎
かみくぼ ていいちろう
糖尿病内科部長(非常勤)
専門
日本内科学会認定医
日本糖尿病学会専門医

大重 聡彦
おおしげ としひこ
糖尿病内科部長(非常勤)
専門
日本内科学会認定医
日本糖尿病学会専門医

田川 理笑
たがわ りえ
糖尿病内科医員(非常勤)
専門
日本内科学会認定医
日本糖尿病学会専門医

加藤 貴保子
かとう きほこ
眼科部長

土居 範仁
どい のりひと
眼科統括部長
専門
医学博士
日本眼科学会専門医
鹿児島大学医学部非常勤講師

水島 崇
みずしま たかし
眼科主任部長
専門
医学博士
日本眼科学会専門医

水島 由佳
みずしま ゆか
眼科部長
専門
医学博士
日本眼科学会専門医

藤原 悠子
ふじわら ゆうこ
眼科医長
専門
日本眼科学会専門医